自然環境との調和(生物多様性保全)
建設業は、事業と生態系との関連性が強いため、自然生態系に与える影響をしっかりと認識し、事業の上流から下流まで一貫して生物多様性保全に取り組むことが重要です。当社は生物多様性保全方針(2010年制定、2019年7月改定)のもと、建設事業の計画・設計・施工、および施工後の各段階において、 ⾃然への影響を可能な限り低減することを⽬指しています。また、自然共生社会の実現に向け、生物多様性を含めた適正な自然資本の利用に取り組んでいます。これらへの対応として、2024年度よりTNFDへの対応に向けて、事業と自然との関係性を整理、自然資本への依存や影響、自然関連のリスクと機会の評価、およびリスク低減と機会獲得のための検討を進めています。
自然の多様な機能を評価し活用するグリーンインフラ、生物多様性の減少傾向を食い止め回復に向かわせる“ネイチャーポジティブ”などに関するさまざまな研究開発を行っています。
生物多様性保全の取り組み
- TNFDへの対応(スコーピング、LEAP分析の実施)およびTNFDに基づく情報開示
- 森林破壊ゼロ方針に沿った「サプライチェーン サステナビリティガイドライン」による木材調達(合法性・持続可能性評価)の実施
- 主要サプライヤーと連携した森林破壊ゼロ方針策定に向けた対話の実施
- 持続可能なコンクリート型枠の採用推進(森林破壊の”チャレンジ・ゼロ“)
- グリーン購入法に基づく特定調達品目の使用
- 生物多様性自主基準の運用
- 在来種植栽実施率の管理指標による生物多様性の質の向上
- 開発事業や工事における環境調査・重要種保護
- 緑地の生物多様性向上のための緑地管理計画・サポート(自然共生サイト認定支援等)
- 建設業における生物多様性保全やグリーンインフラに関する自社独自手法の研究開発・実装(ネイチャーポジティブ定量評価手法、ICTを活用した生態系サービスモニタリング手法など)
顧客のネイチャーポジティブに向けた取組の支援
2022年に生物多様性に係る世界目標である「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択され、2030年までのグローバルミッションとして、ネイチャーポジティブ(自然再興)の実現が掲げられました。こうした状況の下、近年、事業者に対しても自然環境の保全・再興への取り組みが求められています。
当社ではそうしたお客様をはじめステークホルダーの皆さまのニーズに対応する一環として、生物多様性のための30by30アライアンス等に加盟し、積極的なOECM※1データベースへの登録や、OECM認定を受けたエリアの管理の支援といった、緑地の生物多様性を向上させる取り組みを支援しています。また、環境省の里地調査では、身近に見られる種の急速な減少が報告されています。こうした身近な生物の保全につながる緑地の創出や適切な維持管理に関する支援等も実施しています。
主な支援事例
- 緑地における動植物の調査
- 生物多様性に配慮した企業緑地等の管理計画の策定
- 自然共生サイト※2(OECM)等認定支援
【用語説明】
※1:OECM:Other effective area-based conservation measures 「保護地域以外で生物多様性保全に資する地域」
※2:自然共生サイト:「民間の取組等によって生物多様性の保全に貢献するような管理がなされている区域」について、日本独自の制度として「自然共生サイト」の認定を実施。OECMのみならず、保護区域に該当する区域も対象としている。
外部イニシアチブへの参画
-
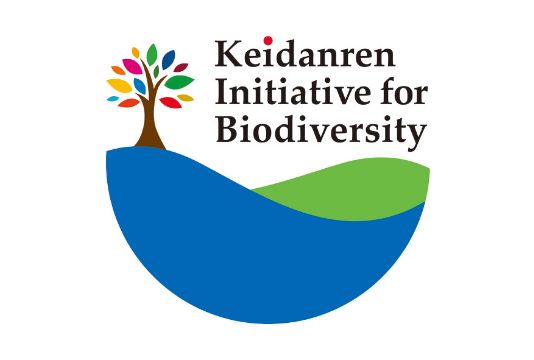
経団連生物多様性宣言イニシアチブ(当社の取り組み方針や活動事例はこちら)
-
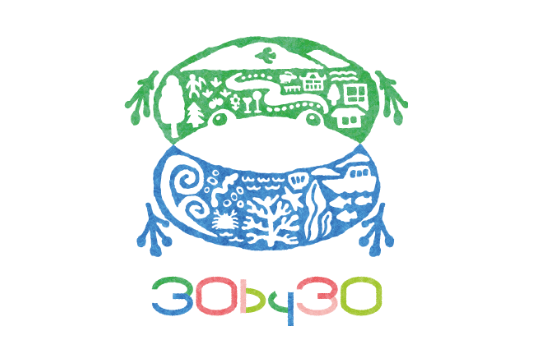
-
